
ポーラの新規事業、冷凍宅食惣菜『BIDISH』、フジテレビ社員と協働で新メニューを開発し2月20日より順次発売
Interview

NTTデータの社内新規事業として発足した「V-BALLER」。VRを活用し、実際の投球データを再現したリアルな打撃体験が可能になるトレーニングシステムで、プロ野球チームからアマチュア野球、個人まで、導入事例が拡大している。2025年2月には、起案者である荒智子がNTTデータからカーブアウトする形でAbZero株式会社を設立。事業をさらにスケールさせるべく奮闘中だ。
荒本人にとっても会社にとっても、簡単ではなかったカーブアウトという決断。その背景には、荒の「覚悟」を感じ全力でバックアップした上長である池田和弘(コンサルティング事業本部 本部長)の存在があった。NTTデータとV-BALLERの事例から見えてくる、大企業とイントレプレナーの幸せな関係とは?
――荒さんが起案し、NTTデータの社内新規事業としてスタートした「V-BALLER」のサービス概要を教えてください。
荒:V-BALLERは、VRを活用した野球のトレーニングシステムです。実際の投球データを再現したリアルな打撃体験により、プロからアマチュア、個人まで幅広い選手層の技術向上や試合感の維持などに役立てることができます。

荒:サービスのポイントは大きく3つあります。1つ目は、360度のVR空間上で実試合における投手の「生きたボール」と対峙できること。身体で体感・理解を深めながらトレーニングができ、苦手な投手や球種に対する反復練習も可能なので、苦手意識の克服にもつながります。
2つ目は、パフォーマンスのデータ化です。VRで投球を受けている時の動きをモニタリングすることで、打者のパフォーマンスをデータ化し、選手ごとのタイミングの取り方、投手や球種、コースといった得意・不得意の把握、選手同士の比較などが可能に。効果的な育成やチーム編成をサポートします。
3つ目は、新たな野球の楽しみ方を多くの人に提示すること。たとえば、プロ野球の球場などに本物のピッチャーの投球データを利用したリアルなバッティングセンターを設置すれば、来場したファンの方に楽しんでいただくことができます。プロ野球の往年の名選手や、応援する球団の選手のリアルな投球をVRによって体感するという、ゲームやピッチングマシンでは得られなかった新たな体験が可能になり、エンゲージメント向上につながります。

――現時点での導入事例や活用方法、利用者の反応などを明かせる範囲で教えていただけますか?
荒:具体的な球団名は明かせませんが、プロチームから社会人チーム、大学、高校、さらにはその下のリトルリーグやシニアリーグまで、導入事例は広がっています。
たとえばプロチームの場合、ユースケースは大きく分けて2つ。1つ目は実際に対戦する投手の球筋を事前にインプットすること。その日の先発投手の映像をiPadなどでチェックしたり、データを確認したりするだけでなく、VRでボールのスピードや軌跡をリアルに体感することで、1打席目から5〜6打席目くらいの感覚で打席に立てるメリットがあります。
2つ目は、パフォーマンスの可視化です。たとえばシーズンの序盤、中盤、終盤、あるいは秋季と春季のキャンプの際などに定期的に計測することで、その選手のスイングのクセ、苦手な投手や球種、コースなどを分析することができます。そのデータをもとに、トレーニングの強化方針を立てられるんです。
また、ゆくゆくは球団スカウトの方を通じてアマチュアのトップ選手にV-BALLERを使ってもらい、各選手のデータを比較することでドラフト戦略に役立てるといったことも可能になるのではないかと考えています。
――各試合でのパフォーマンス向上、技術レベルの底上げ、さらにはチームの強化戦略と、さまざまな使い方ができるわけですね。
荒:そうですね。一方、高校野球ではユースケースがまるで変わります。高校の場合、技術の向上以前に「練習格差」の問題があります。練習環境にも対戦相手にも恵まれた強豪校がある一方で、なかには練習試合を頻繁に組むことができない、色んな球種を投げられる練習相手がいない、グラウンドや室内練習場を十分に確保できないなど、さまざまな課題を抱えた学校も数多くあるんです。そんな場合でもこのツールがあれば、いつでもどこでも、一人でも実践的な練習ができる。環境的なビハインドを埋めていくことが可能になります。

――導入した高校の野球部員からは、どんな反響がありましたか?
荒:今の高校生たちはデジタルネイティブなので、こうしたデジタルツールを使うこと自体への抵抗感はなく、受け入れもスムーズでした。また、ゲーム感覚というか、楽しみながらできる点も良かったようです。同じ素振りをするのでも、バーチャルとはいえ投手の球を見ながらバットを振れるため、非常に楽しいと。新しい練習プログラムとして非常に好評でしたね。
また、離島の高校の野球部にもお使いいただきましたが、そうした環境だとやはり指導者も少ないですし、頻繁に遠征や合宿をするのも難しい。そもそも野球部員がギリギリ9人揃うかどうかというケースもあり、それまでは実践的なトレーニングを積むことができなかったと。そんななかで、V-BALLERが非常に役に立ったというお声はいただいています。
――V-BALLERはもともと荒さんが起案した事業ということですが、あらためて立ち上げの経緯を教えてください。
荒:NTTグループ内には複数の研究所があり、幅広い分野でさまざまな研究開発が行われています。そのうちの一つに、360度のVR空間で球の動き(スピード、軌跡)をリアルに再現するアルゴリズムの研究があったんです。NTTデータを含むグループ内でこれをどう活用していくかという検証の場が設けられた時に、個人的に大きな可能性を感じ、どうにか形にできないかと思ったのがきっかけですね。
――特に、どんな点に可能性を感じましたか?
荒:一番は最初からグローバルな展開をイメージできたことです。野球でいえば国内のスポーツ市場はダントツで大きいのですが、アメリカはその何倍もの市場規模があります。また、ゆくゆくは野球だけでなく色んなスポーツにも展開してくことを考えると、世界中のスポーツ市場をターゲットにできるビジネスになるのではないかと考えました。また、スポーツは万国共通のエンタメであり、文化や価値観の違いによるハードルも低い。ローカリゼーションという壁を気にすることなく、シンプルに海外へ持っていくことができる点も強みではないかと。
個人的に、日本の産業を強くしたい、外貨を稼げるグローバルな事業に携わりたいという思いをずっと持っていたこともあり、ぜひチャレンジしたいと思ったんです。
――ちなみに、荒さんはもともと野球好きだったのでしょうか?
荒:正直に言うと、この事業に携わるまでは野球に特別な関心を抱いていたわけではありません。ただ、V-BALLERを推進する過程で関係者の方にお話を伺うにつれ、魅力を感じるようになりました。特に驚かされたのは、日本の野球技術の高さです。先日も「名球会」(※)の方にお話を伺ったのですが、こと技術という点で観れば日本人の資質は世界トップレベルにあるとおっしゃっていました。
野球では特に、イチロー選手や大谷選手の名前を出すまでもなく、そのポテンシャルが見えてきていますよね。ただ、そうした才能を埋もれさせないためには、国土の狭さをカバーする練習環境が必要です。それをVRによって補うことで、第二・第三のイチロー選手、大谷選手が世界で活躍する未来へとつながるのではないかと思います。
※日本プロ野球名球会:日本のプロ野球(NPB)、アメリカのメジャーリーグ(MLB)において日米通算2000本安打・200勝・250セーブを達成した現旧プロ野球選手の会員組織。

――池田さんは、もともと荒さんが所属していたコンサルティング事業本部のトップですが、当初、V-BALLERの事業化の可能性をどう見ていましたか?
池田:私自身は2023年に前職のボストンコンサルティングからNTTデータに入りました。当時、コンサルティング事業本部内で新しいビジネスをつくる法人アセットベースドサービス(ABS)推進室では、複数の事業アイデアが同時進行で動いていて、V-BALLERもその一つでした。ビジネスプランの完成度や解像度については高いとは言えない状態でしたが、非常に大きな可能性を感じさせるものであったと思います。
特に良かったのは、ビジネスとして非常に広がりが見えた点。プロ野球だけでなく、小中高の野球部や社会人野球にも展開していく。また、将来的には他のスポーツにも転用していくんだと。さらには、障がいを持つ方にも野球を楽しんでもらえるツールとしての活用も視野に入れていて、非常に広がりのある、チャレンジングな企画であるという印象を持ちました。

――その一方で、課題はどのように捉えていたのでしょうか?
池田:アイデア自体は良かったのですが、私が入った時点ではビジネスを大きくしていくシナリオがまるで描けていない状態だったんです。また、そもそも新しく市場を作らなくてはいけない難しさもありますし、初見では導入効果をイメージしづらいツールでもあるため、お客さんがつくまで時間がかかるだろうという見立てもありました。そこで、まずは荒やチームのメンバーと「この事業をどうやってスケールさせていくか」の議論を積み重ねるところからスタートしました。
――池田さんは外部からジョインした立場として、NTTデータの新規事業に対する姿勢などはどう感じましたか?
池田:まず、チャレンジに対しての許容度が高い会社だと感じました。たとえ現時点で顧客がいなくても、社会的に意義があったり、何かの課題を解決できるものであると判断されれば、事業化を目指すことができます。
一方で、これはどの企業も変わりませんが、そのチャレンジに対して「結果の良し悪し」で判断されるところがある。チャレンジは結果も大事ですが、次のステップへ進むための検証や仮説の材料をどれだけ得られるかも同じくらい重要です。全てのチャレンジは「実験」であるという捉え方をすれば、ビジネスとして芽が出なかったり、社会的に大きなインパクトを与えられなかったとしても失敗にはなりません。そうした寛容性を持つことが、NTTデータのみならず日本全体の課題であるように思います。
――2025年2月にはNTTデータからカーブアウトし、荒さんが代表を務めるAbZero株式会社がV-BALLERの事業を引き継いでいます。会社としても、荒さん個人としても簡単ではない決断だったと思いますが、あらためて経緯を教えてください。
荒:この事業がスタートして2年ほど経過した頃に、「継続するか、辞めるか」の決断を迫られました。詳細は省きますが、結果的にコンサルティング事業本部として注力していく領域から外れているとの判断が下り、現部署でV-BALLERを続けていくことが難しくなってしまったんです。ただ、すでにお客さんも付いていて、中途半端なタイミングでの撤退は色んな人に迷惑がかかる。私のなかで辞めるという選択肢はありませんでした。
じゃあ、続けるためにはどうすればいいか。その時点では複数の方法が考えられました。NTTグループ内の別会社で引き継ぐ形や事業売却など、さまざまな可能性を探るなかでカーブアウトという選択肢が浮上してきたという流れですね。といっても、私のなかで浮上していただけで、他にそんな考えを持っていた社内の人間は誰もいなかったと思いますが(笑)。

――そこから荒さんのなかで、どのようにカーブアウトへ気持ちが傾いていったのでしょうか?
荒:まずはM&Aの知見を持った方などにヒアリングを重ねました。事業売却を含めたさまざまな選択肢をフラットに並べ、メリット・デメリットを整理していったんです。ただ、最終的には理屈どうこうではなく、「自分の手でやりきりたい、チャレンジしたい」という思いが勝りました。大企業の新規事業の出口としてカーブアウトという事例も少しずつ出始めていましたし、これからもっと、そうした選択肢が増えるべきだという思いもあって、徐々にカーブアウトへと気持ちが傾いていきましたね。
とはいえ、もちろんNTTグループとして前例のないことですので、許してもらえる望みは薄いと思っていました。ですから、オフィシャルな場で意思を伝える前に、まずは池田さんに「あくまで個人的な相談で」みたいな形で切り出したんです。「私としてはカーブアウトして、自分の手でV-BALLERをスケールさせたいです」と。そうしたら、意外にポジティブな反応が返ってきて、あれ?意外とアリなのかなと思いました。実際には、そこから池田さんが会社と何度も折衝を重ねてくれて、ようやく実現したわけですが……。本当に感謝しています。

池田:自分でやりたいと荒が言ってきた時に、僕は「覚悟はあるのか?」と問いました。これまでは、企業のお金でビジネスを作ってきた。カーブアウト後はそうではなく、自分でお金を出してまでやる覚悟が必要ですから。そう聞くと彼女は「それでもやりたい」と。この事業を伸ばすにしても畳むにしても、自分が最後まで面倒を見たいと言う。だったら、もう道は一つしかないよねと。
もちろん前例がないため、社内稟議の通し方を含めてイチからプロセスを構築していきました。苦労はしましたが、新しいスキームができたことで、次に荒のようなケースが出てきた時に同じ選択肢を取りやすくなる。だからといって会社が積極的にカーブアウトを推奨することはありませんが、大企業内新規事業の出口として、選択肢が増えるのは非常に良いことだと考えています。
――NTTデータがカーブアウトを承認したことは、社内だけでなく外部の人たちにも大きなインパクトを与えたと思います。特に、同じく大企業で新規事業に取り組む人にとっては、「そんな選択肢もあるのか」と、羨ましく映りそうです。
池田:正直、NTTデータとしてもカーブアウトを100パーセント「是」としているわけではありません。これまで多くの投資をし、技術も活用してきて、それらを十分に回収できたとは言えない状態で出ていかれるわけですから。
ただ、あくまで個人的な意見として、荒の後に続く人間がどんどん出てくることは、長い目で見ればNTTデータにとって、もっと言えば日本にとってプラスになるのではないかと思います。たとえば、荒がV-BALLERを成功させることで、古巣のNTTデータや事業が立ち上がった経緯があらためてクローズアップされるかもしれない。そこにはビジネス上のメリット・デメリットを超えた価値があると思います。

――企業とイントレプレナーの関係性として、理想的な事例の一つになるかもしれません。
池田:これからの時代は特に、AIの拡大によって人同士の交わりがチープになっていく可能性があります。そんななかで新規で事業を作るということは、新しく人と人をつなげるという意味でも大きな価値があるでしょう。
荒が独立した後も、NTTデータとの付き合いが完全に途切れるわけではありません。たとえビジネス上の関係性はなくなったとしても、社内には荒が頑張ってきた姿を見てきた人間がたくさんいます。そうした人とのつながりが消えることはないだろうし、僕自身も引き続き、可能な限りサポートをしていきたいと思っています。
取材・執筆:榎並紀行(やじろべえ株式会社) 撮影:松倉広治
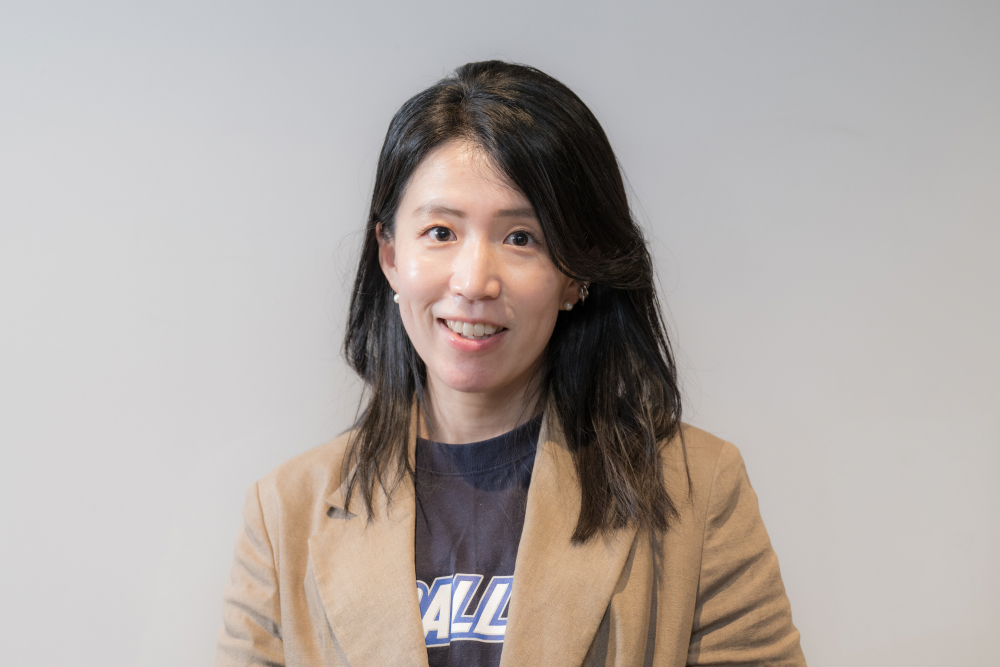
AbZero株式会社
荒智子
NTTデータ社入社以来、メディアやエンタメ業界における新規サービスの立上げ、国内外への展開等、Business Developmentに従事。 2016年からは、スポーツ×IOTの分野で新規事業として、「V―BALLER」事業を立ち上げ、選手のパフォーマンス向上及びファンエンゲージメントの両面でNPB、MLBといったプロ向けからアマチュア、自治体含めて幅広く展開中。XR技術をトレーニングやファンサービスに取り入れることで、新しい気付き、体験を世界へ提供する。 NTTデータから事業譲渡により「V-BALLER事業」を引き受け、新たなスポーツ体験を日本から世界へ広めることを目標にAbZero株式会社を新規創業。

株式会社NTTデータ
池田和弘
外資系の事業会社にて10年の営業、マーケティング部門を従事、その後、人事、総合コンサルティングを経験、直近ではボストンコンサルティンググループを経て、2023年4月にNTTデータに入社。23年以上、様々な業界の企業でマーケティング、販売戦略開発、新しい組織構築に携わってきており、様々な企業の戦略策定と実行、システム導入のサポートなどを経験。デジタルトランスフォーメーションや新規事業戦略など、業界を超えたプロジェクトに取り組んできた。専門分野は、新規事業開発、戦略コンサルティング、デジタルトランスフォーメーション、組織設計、変更管理と学習開発、マーケティングと販売戦略など。情熱とコラボレーションの精神を持って、組織の能力構築とコーチングを積極的に奨励している。